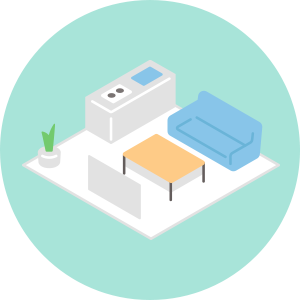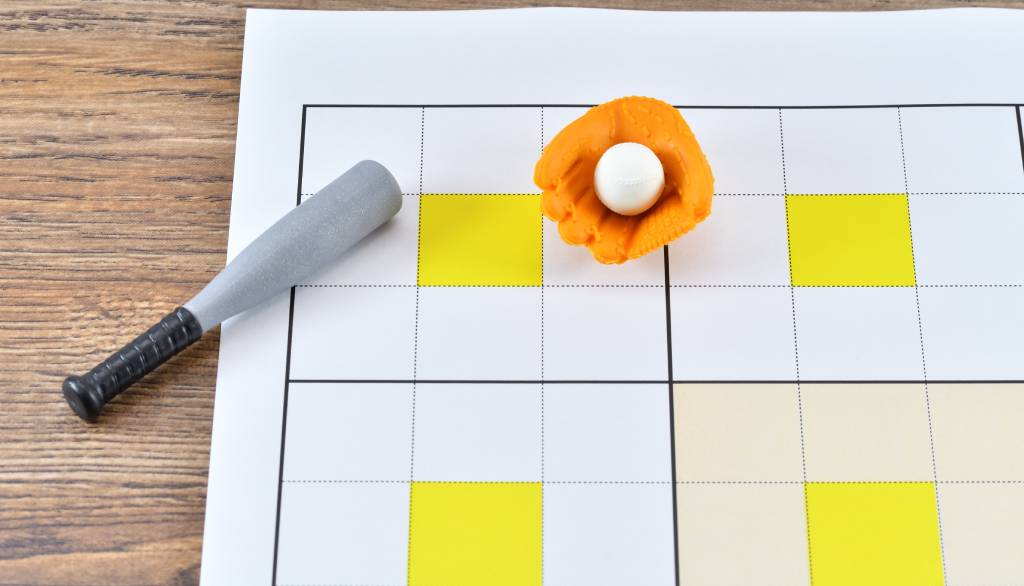
マンダラチャートとは? 大谷翔平選手に学ぶ、目標設定のポイント
やるべきことが多くて頭がいっぱいになっている時ほど、シンプルなフレームに書き出して整理すると、優先順位がはっきりするものです。
そのフレームの一つに、大谷翔平選手が高校時代に使っていたと話題になった「マンダラチャート」というものがあります。
このチャートは大谷選手のようなスポーツ選手だけでなく、会社員、学生、主婦など、あらゆる立場の人に役立つツールです。
今回は、マンダラチャートについて大谷翔平選手の実例を参考に、作り方を解説します。
マンダラチャートとは?
「マンダラチャート」という言葉を初めて聞いた方もいると思いますが、これは思考を整理し、目標を達成するための日本生まれのツールです。
紙とペンさえあれば誰でも今すぐ始められるシンプルな構造でありながら、やるべきことがどんどん明確になっていく深さがあります。
松村寧雄氏が考案した日本発の目標管理ツール
マンダラチャートは、株式会社クローバ経営研究所の創設者である、松村寧雄氏が発案したものです。
当初は経営戦略や組織運営のためのフレームワークとして使われていましたが、その後は教育やスポーツ、自己啓発の分野にも広がりを見せました。
このチャートの構造は非常にシンプルで、9×9=81マスの枠を使って、中心に「達成したい目標」を書き込みます。
そして、その目標を支える8つの要素を周囲に配置し、それぞれをさらに具体的な行動やアイデアに分解していくという流れになります。
多くのフレームワークが「分析」や「戦略」に偏りがちな中、マンダラチャートは「行動」に重きを置いているのが特徴です。
9×9のマス目を使って目標を中心に思考を広げる
マンダラチャートの使い方は以下のようなイメージです。
1.中心(真ん中の1マス)に「最も大切な目標」を書く
2.その周囲8マスに、目標達成に必要な要素(分野・視点)を書き出す
3.さらにそれぞれの要素を細分化して、実行レベルのアイデアを配置していく
例えば「英語を話せるようになりたい」という目標を中心に置いた場合、周囲の8マスには「語彙力」「文法力」「リスニング」「スピーキング」「学習時間の確保」「教材選び」「モチベーション維持」「実践機会」などが入るでしょう。
さらに、それぞれの分野に対して「毎日30単語を暗記する」「YouTubeで1日15分の英語動画を見る」「オンライン英会話に週2回参加する」など、具体的な行動が加わります。
視覚的に一覧化することで、「なんとなく頑張る」から「何をどう頑張るか」に行動が切り替わっていきます。
「可視化する思考法」として、教育や企業研修にも導入
マンダラチャートは現在、全国の中学、高校、大学の教育でも導入されており、主に将来の理想像を書き込み、必要なスキルや資格、経験を洗い出すという使われ方をしています。
また、企業研修で「目標管理」や「プロジェクト設計」の一環として導入されるケースも増えていて、会議などの場面ではマンダラチャートを使ってアイデア出しを行うと、論点がブレないといったことから重宝されています。
視覚的に整理されたチャートは記憶にも定着しやすく、行動にもつながりやすいため、教育現場でもビジネス現場でも役に立っているのです。
大谷翔平選手が作ったマンダラチャートの実例
プロ野球選手として、日本とアメリカの両方で圧倒的な実績を残し続けている大谷翔平選手ですが、そんな彼の土台を築いたもののひとつが、高校1年生のときに作成したマンダラチャートでした。
作成されたそのチャートは、当時から大谷選手の強い意志と計画力を示しており、書籍やドキュメンタリーでも多く取り上げられ、実際に参考にする人も多く見られます。
高校時代に作成された「ドラフト1位指名」を達成するための図解
花巻東高校に入学したばかりの頃、大谷選手は「ドラフト1位で8球団から指名されてプロ入り」という明確な目標を設定しました。
そして、その実現のために自分に必要な8つの要素を考え、マンダラチャートに落とし込んだのです。
そのチャートには、「体づくり」「コントロール」「キレ」「スピード160km/h」「変化球」「運」「人間性」「メンタル」といったカテゴリが並び、それぞれに具体的な行動が書き込まれています。
例えば「体づくり」には、「体のケア」「サプリメントを飲む」「FSQ90キロ」「RSQ130キロ」「食事夜7杯朝3杯」「可動域」「スタミナ」「柔軟性」といった、数値や行動で測れるタスクが含まれていました。
この設計によって、彼は毎日の練習に対して「何を意識するべきか」を明確にできていたといわれているのです。
目の前の練習が、目標達成のどの部分に繋がっているのかを理解しているからこそ、淡々と継続できたのでしょう。
マンダラチャートの具体的効果
大谷選手のチャートが優れていたのは、目標に対して必要な項目が網羅されていた点だけではありません。
例えば、「人間性」という抽象的な要素も「感謝」「礼儀」など、日常的な行動に細かく落とし込まれており、野球の技術だけでなく、人としての在り方も意識的に高めていたのです。
周囲との関係性やメディアへの対応、ファンへの振る舞いからも、こうした積み重ねが見て取れます。
また、「メンタル」の欄には「一喜一憂しない」「ピンチに強い」「勝利への執念」などの要素が並び、これらも日々の行動としてトレーニングされていて、大舞台でも結果を出し続けられる理由になっているようにも感じられます。
今日から使えるマンダラチャートの作り方

まずは中心に「最終目標」を置くところから始める
最初にやるべきなのは、チャートの中心マスに自分が「心から達成したい目標」を書き込むことです。
これは大きな夢である必要はなく、「3ヶ月以内に3kg痩せる」や「TOEICで700点を取る」など、具体的かつ明確なものが望ましいです。
なお、「心から」とあるように、達成に対する本人の強い思いがあることが前提となります。そのため、もし気持ちや感情の意識化が不得手な場合は、コーチングなどを利用して自己開示のサポートやトレーニングを受けることで「心から」の強い思いを言語化しやすいかもしれません。
目標設定のコツとしては、以下の3つを意識すると良いでしょう。
1.数字で測れる(例:月収30万円、副業月5万円など)
2.期限がある(例:3ヶ月で、年内に、○月○日までになど)
3.主語が「自分」である(例:「上司に○○」ではなく「自分が○○」など)
この「中心の目標」が自分の中にある欲求や理想を言葉でしっかり明確になっているかどうかで、全体の質が決まります。
8つの関連要素を具体的に書き出すためのポイント
中心の目標を決めたら、次に取り組むのはその周囲8マスの記入で、ここには目標を達成するために必要な要素、分野、視点を書き出していきましょう。
例えば目標が「3ヶ月で5kg減量する」なら、以下のような要素が考えられます。
1.食事改善
2.運動習慣
3.睡眠管理
4.体重記録
5.モチベーション維持
6.知識収集(栄養、ダイエット)
7.周囲のサポート
8.ストレス対策
この時点で何を頑張れば良いのかがかなり整理されてきます。
ビジネス系の目標の場合は「スキルアップ」「顧客対応」「マーケティング」「時間管理」「収益モデル」などが入る場合が多く、受験や資格取得なら「過去問分析」「暗記力強化」「集中時間の確保」などが挙げられるでしょう。
1マスずつ「どうすれば実現できるか?」を掘り下げていく
8つの要素が出揃ったら、いよいよ「外枠」の記入に入ります。
ここではそれぞれの要素に対して、「具体的にどうすればその項目を達成できるか?」という行動を細分化して書き込みます。
例えば、「運動習慣」という要素に対しては「朝に10分ウォーキングする」「週2回ジムに行く」「寝る前にストレッチする」といったように、日常的な行動にまで落とし込むのが理想です。
ここで意識したいのは、しっかりと継続できるように、今の自分が無理なくできそうな行動を設定することです。
ここまで作り終えると、1枚の紙に今やるべき行動がずらりと並ぶので、あとはその項目を毎日少しずつ実行していくだけになります。
理想の自分に近づくために活用してみよう!

自分の理想とそこに至る具体的な行動をすべて書き出し、頭の中でぼんやりしていた「やりたいこと」が「やれること」に変わっていくのが、マンダラチャートの魅力です。
どのようなテーマにも使えるので、やりたいことがあるのに動けなかったり、努力しているのに成果が出なかったりというようなお悩みがあれば、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか?

コーチングは現在、ビジネスの場面をはじめ、プライベートの場面においても広く用いられるようになってきています。
それは、コーチングが人の「強み」を伸ばし、行動化をサポートする新しいコミュニケーションの技術であることが理由かもしれません。この技術の新しさは、相手の不平や不満という負の感情さえも、建設的な力への転化が可能であることです。
さらに注目したい画期的な効果として、コーチングが「違い」を活かし合う創造的なコミュニケーションの手法であることから、
相性や性格、価値観が合わない相手との対応力を向上させることも可能にしてしまう点です。
結果として、自分のコミュニケーション能力の飛躍的な向上やリーダーシップなどの幅を広げることに役立てられます。
コーチングは「自分らしさ」も「相手らしさ」も大切にし、「お互いを高め合う」コミュニケーションの手法ともいえます。
老若男女、職種などに関係なく学習し、さまざまな場面で活用できる技術です。